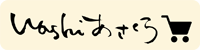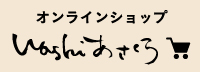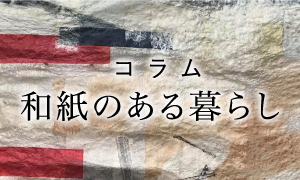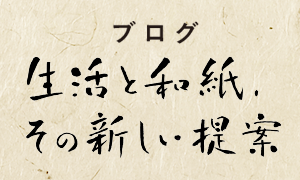和紙専門店が教える!和紙に関するよくある質問集(Q&A)
2019年03月29日
1897年創業、1世紀以上にわたり和紙と共に歩んできた当店が、お客様からよくいただくご質問にお答えします。和紙の歴史や特徴、選び方、劣化を防ぐ方法など、専門知識と経験に基づいた情報をお届けします。和紙について知りたい方は、ぜひご覧ください。
和紙の基礎知識に関する質問
和紙の特性や用途に関する質問
和紙の取扱いに関する質問
和紙の歴史や文化に関する質問
和紙を購入したい場合の質問
よくある質問は、お客様の声を参考に随時更新してまいります。ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお寄せください。
また弊社のブログでは、和紙で暮らしをより豊かにするヒントとなるような情報も発信しております。ぜひご覧ください。
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:手漉き和紙の乾燥方法「板干し・鉄板乾燥」仕上がりの違いとは?
2018年12月15日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****
手漉き和紙の製造工程における乾燥方法には「板干し」と「鉄板乾燥」の2種類があり、それぞれに特徴があります。乾燥方法の違いと、仕上がる和紙の性質の違いについて解説します。
手漉き和紙の乾燥方法
伝統的な「板干し」
晴れた日に紙漉きの産地を訪れると、大きな板に白い紙が貼り付けられ、天日干しされている光景を目にすることがあります。周囲の緑に映える白い紙は、とても美しい光景です。

しかし、この美しい光景の裏には、一枚一枚「紙つけ刷毛」を使って干し板に貼り付け、天日で乾かすという、気の遠くなるような重労働があります。干し板は約10キロ前後ほどの重さがあり、乾いたら取り込んでまた次の干し板を外に出します。天候に左右されるため、梅雨時期など、雨の日が続けば作業が滞ってしまうこともあります。乾燥中の紙が雨でぬれるとシミができたり、カビが生えたりする可能性もあるため、ひと時も目を離せません。
乾燥時間は夏場は1時間ほど、冬なら半日程で干せます。干しあがった和紙には、薄っすらと木目が転写され、独特の風合いがあります。板干しした和紙はこちらの記事でご覧いただけます。
天候に左右されない「鉄板乾燥」
そこで登場したのが「三角乾燥機」を使った鉄板乾燥です。三角形の鉄板に紙を貼り付け、中に蒸気を送り込んで鉄板を温め、紙を乾燥させます。かつては鉄板が錆びて紙に悪影響を与えることもありましたが、現在ではステンレス板を使用することで、その心配もなくなりました。

形状は三角以外にも一面や二面のものなどがありますが、三角乾燥機は効率も良いため、最も多く見られます。鉄板乾燥の最大のメリットは、天候に左右されず、場所も取らずに効率的に乾燥できることです。そのため、現在ではほとんどの手漉き和紙が、この方法で乾燥されています。
板干しと鉄板乾燥、それぞれの違いとは?
板干しと鉄板乾燥では、出来上がる和紙にどのような違いがあるのでしょうか?
1.紙のしなやかさ
板干しで乾燥させた和紙は、鉄板乾燥のものに比べて、しなやかさが増します。これは、乾燥温度の違いによるものです。鉄板乾燥は高温で行われるため、紙に残る水分が少なくなり、硬くなってしまうのです。長時間放置すれば、両方の紙の水分率は同じになりそうですが、実際にはそうはならず、この違いはいつまでも残るようです。
2.紙の強度
板干しで乾燥させた和紙は、鉄板乾燥のものに比べて、強度があります。紙の原料である植物繊維は、水に濡れると膨らみます。それを板や鉄板に貼り付けて乾燥させると、繊維が収縮し、強度が生まれます。
板と紙は、どちらも植物由来の素材であるため、収縮率がほぼ同じと言われています。そのため、紙が乾燥する際に木の板と一緒に収縮し、無理なく水素結合が行われ、強い紙になるのです。
一方、鉄板は紙と収縮率が違います。特に鉄板乾燥機では温度が一定に保たれるため、紙だけが収縮しようとします。その結果、紙の組織の一部が壊れ、水素結合が十分できず、板干しで乾燥させた和紙と比べると、弱い紙になってしまうのです。
まとめ
普段あまり知る機会のない乾燥方法ですが、他にも使用する原料の種類や産地、原料の処理方法などによって、実に様々な性質の和紙が出来上がります。たくさんの情報を知れば知るほど、どの和紙を選べばよいか迷ってしまうかもしれません。もし和紙選びに迷ったら、求める質感や予算など「外せないポイント」と「使用目的」を明確にしておくと、希望とする和紙を見つけやすくなります。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:長持ちする和紙の選び方はありますか?
2018年11月06日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

長期保存性に優れた和紙をお探しのお客様からのご質問です。大切な作品や記録を残す際には、長く美しい状態を保てる和紙を選びたいものです。そこで今回は、長期保存に適した和紙を選ぶ際のポイントを分かりやすく解説いたします。
和紙を選ぶ際のポイント
長持ちする和紙を選ぶためのポイントは、以下の2点です。
- 国産原料100%使用&灰煮処理されていること
- 非塩素漂白であること
これらのポイントは、和紙の長期保存性に大きく関わってきます。具体的にどのような影響があるのか、詳しく見ていきましょう。
なぜ国産原料100%&灰煮処理が重要なのか?
海外産の原料は品質が安定しない場合があり、また油脂分を多く含みます。そのため、製造時に強い薬品での処理が必要となり、繊維が傷んでしまいます。また、洋紙原料のパルプを混合することも保存性に悪影響を与えます。なぜなら、化学パルプはさらに強い化学処理を受けて製造されているからです。
一方、国産原料は品質が安定しており、原料を煮る際にマイルドなアルカリ性の灰汁を用いることで、繊維へのダメージを最小限に抑えられます。また、水洗工程でも繊維中にアルカリ分が残留しやすく、できた製品が弱アルカリ性となることで、酸化から和紙を守る効果も期待できます。
塩素漂白が及ぼす影響とは?
普段目にする「白い和紙」の多くは、塩素系漂白剤を使用して作られています。しかし、漂白剤の使用は繊維を傷つけ、微量の塩素が残留すると、色あせや変色、経年劣化の原因となります。
手漉きか機械漉きかは保存性に影響しない
手漉き和紙と機械漉き和紙は、製造方法が異なりますが、適切に作られたものであれば、保存性に大きな違いはありません。どちらを選ぶかは、用途や好みに合わせて決めて問題ありません。
まとめ
ここまで説明した条件を満たす和紙の代表例として「文化財・古文書修復用和紙」が挙げられます。この種類の和紙は、長期保存を目的として作られており、高い耐久性と保存性を備えています。手漉き・機械好きどちらも作られています。
ただし、文化財・古文書修復用和紙にも様々な種類があります。購入する際は、上記で説明したポイントに加え、必要な厚さや用途に合わせて選ぶようにしましょう。大切な作品や記録を末永く残したい方は、ぜひこれらのポイントを参考に、最適な和紙を選んでみてください。
※参考記事
和紙の劣化を加速させる主な要因について解説しています。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:和紙とは何ですか?
2018年10月28日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

「和紙」という言葉は、私たち日本人にとって馴染み深いものですが、改めて「和紙とは一体何なのか?」「ほかの紙と何が違うのか?」と問われると、明確に答えられる人は少ないかもしれません。今回は、そんな和紙について分かりやすく解説していきます。
和紙とは?
和紙とは、日本古来の製法で作られる紙の総称です。本来、和紙は国産の楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)などの植物の靭皮(じんぴ)繊維を原料とし、国内で手漉き(流し漉き)によって作られるものを指していました。
しかし、現代では、手漉きだけでなく機械漉き(抄き)の和紙も存在し、原料も海外産や木材パルプを混ぜるなど、その定義は多様化しています。こちらの記事で現在の和紙の定義をご覧頂くと、かなり網羅性が高いことがわかります。このような状況の中、以前ご紹介した「美濃和紙と本美濃紙」のように、昔ながらの製法の和紙を守る目的で、呼び名を分けた産地もあります。
- 流し漉き(ながしずき)とは
和紙の紙料液を簀桁をすくい、縦横に動かし繊維を絡みあわせる日本独自の漉き方
- 溜め漉き(ためずき)とは
和紙の紙料液を簀桁の上に溜め、水分が下に落ちるのを待って紙層を作る中国古来の漉き方。紙作りの技術が中国から日本に伝わった当初は、この溜め漉きが主でしたが、やがて日本独自の流し漉きへと発展しました。
和紙の歴史
和紙の歴史は古く、飛鳥時代にはすでに紙が作られていたという記録が残っています。その後、平安時代には貴族の間で行われた和歌、漢文、書などに用いられ、日本文化の発展に大きく貢献。江戸時代には、庶民の生活にも和紙が深く浸透し、障子紙や傘など様々な用途で利用されるようになりました。
明治以降、西洋文化の流入とともに洋紙の普及が加速し、和紙の生産量は減少の一途をたどります。しかし近年では、和紙の持つ独特の風合いや環境への配慮といった点が再評価され、伝統工芸品としての価値が見直されています。
和紙の主な機能性
和紙は、古くから日本人に親しまれてきた伝統的な紙ですが、その機能性も非常に高く評価されています。現代においても、その特性を生かした様々な製品が開発され、私たちの生活に溶け込んでいます。
- 素材感の良さ
長い繊維が絡み合って出来た和紙は、自然素材ならではの温かみのある表情や、優しい触り心地が特徴です。3大和紙原料「楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)」それぞれに特徴があり、多様な用途に活用できます。
- 高耐久
強靭な繊維を持つ和紙には、1000年以上の保存に耐えるものもあります。和紙の持つ柔軟性や経年による変化が少ないことから、国内外問わず、重要無形文化財や絵画の修理修復などにも使われています。
- 染色や加工に耐えうる強靭さ
和紙は水を含ませながら行う染めや折りなど、様々な加工が出来るので表現の幅が広がります。一方、洋紙はパルプを主原料としているため繊維が短く、特に水を使った加工を行うとボロボロになります。
- 紫外線・赤外線カット効果
光が透過する際に和紙の繊維で乱反射がおこるため、肌に有害な「紫外線」を90%前後カットする効果があります。また、暑さを感じる「赤外線」も80%前後カットするので、和室の障子は夏を涼しく過ごすため、理にかなったものなのです。
- 調湿・空気浄化作用
和紙には湿気が多い時には吸収し、乾燥しているときには放出する自然の調湿効果があります。また、和紙繊維がフィルターの役割を果たし、花粉やホコリなどを吸着。消臭作用もあり、自然の力で快適な室内環境をつくります。
まとめ
古くから人々の暮らしに根付いてきた和紙は、その温かみのある風合いと、自然素材ならではの優しさが魅力です。環境問題が深刻化する中、伝統的な製法で作られる和紙は、自然に優しい素材として注目を集めています。
照明を通した美しい透け感や、和紙アートパネルなど空間を演出するアイテムとして、和紙は伝統工芸としての価値を守りながら、現代のインテリアやデザインにも幅広く取り入れられています。今後も、和紙は私たちの生活に新たな価値をもたらし続け、より豊かな暮らしへと導いてくれるでしょう。
※参考記事
日本における和紙の定義と、弊社の考えについて解説
和紙の良いところと悪いところを解説
和紙と洋紙を見分けにくい要因について解説
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:和紙の魅力とは?
2018年09月27日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

完成された美しさ、そして無限の可能性
弊社は和紙専門店として、日々和紙と向き合っています。その中で常に感じているのは、和紙が持つ二つの魅力です。
一つ目は、和紙がそれ単体で美しく完成されたものであるということです。自然の素材である楮や三椏、雁皮といった原料から作られる和紙は、その一つ一つに個性があり、見ているだけで心が安らぎます。
二つ目は、和紙が未完成の状態ともいえるということです。言い換えると、和紙は想像力を働かせることで、どんな形でも思いにも応えてくれる万能の素材なのです。
懐の深い和紙
和紙は使う人の想像力を刺激し、どんな形にも変化します。ハサミで切り絵のようにカットすれば、繊細な模様が浮かび上がり、ちぎれば繊維がほつれて自然な風合いが生まれます。また重ねて貼り合わせれば、形や厚み、強度を自在に変えられ、透かしてみれば奥行きのある表情が現れます。その多様な表情は、作品制作のみならず、ファッションやインテリアなど、私たちの生活を豊かに彩ります。
原料の違いで生まれる個性
和紙の原料の種類や配合、そして製法の違いによって、出来上がる和紙の表情は実に様々です。下記に、代表的な和紙原料を使った場合の特徴をまとめました。
- 楮(こうぞ)
和紙の代表的な原料であり、最も多く使用されています。太く長い繊維が特徴で、力強さと温かみを兼ね備えた風合いが魅力です。
- 三椏(みつまた)
きめ細かく、柔らかな肌触りと優しい光沢感が特徴です。少し黄みがかかった上品な色合いも魅力の一つ。
- 雁皮(がんぴ)
繊維は細く光沢があります。漉き上がった和紙は、表面が滑らかで上品な光沢を放ち、透き通るような透明感があります。
和紙を眺めるだけで心が癒される
お客様の中には、和紙を眺めてその美しさを楽しむために購入される方もいらっしゃいます。この気持ち、私たちもよく分かります。
なぜ、人は和紙に癒されるのでしょうか?
その理由の一つに、1/fゆらぎの存在が考えられます。1/fゆらぎとは、自然界に多く見られる、不規則でありながらも一定のゆらぎを持つ現象のことです。例えば、川のせせらぎの音、木の葉が風に揺れる様子などが挙げられます。この1/fゆらぎを持つものを眺めたり感じたりしていると、心が落ち着き、リラックス効果をもたらすと言われています。
自然素材から作られ、人の手によって一枚一枚漉かれた和紙には、その過程で生まれる繊細な繊維の動きが見られます。これらの不規則な模様は、まさに1/fゆらぎそのもの。和紙を眺めたり、触れたりすることで私たちは心地よさを感じ、心が安らぐのです。
今回、弊社が日々感じている和紙の魅力についてご紹介しました。これは、和紙が持つ魅力のほんの一部に過ぎません。
和紙は単なる紙という枠を超え、私たちの生活を豊かにしてくれる存在です。生きていく上で必ずしも必要なものではないかもしれませんが、和紙があることで日常がより豊かになり、心に潤いを与えてくれます。
今後も和紙の魅力を広く発信し、より多くの方々に「和紙のある豊かな暮らし」をご提案してまいります。
※参考記事
和紙を使ったDIYアイデアを一覧でご紹介しています。
始めて和紙を購入するときに参考となる、購入場所や選び方のポイントについて解説しています。
癒し効果のある和紙のホスピタルアートに関する研究を行いました。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:なぜ手漉き和紙は少なくなってしまったのでしょうか?
2018年09月05日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

日本の伝統工芸品として、書道や絵画、工芸品など様々な用途で愛されてきた手漉き和紙。しかし、その生産量は増加するどころか減少の一途をたどっています。一体なぜ、手漉き和紙は少なくなってしまっているのでしょうか?今回は、その背景にある要因をいくつかご紹介します。
手漉き和紙減少の要因
後継者不足
手漉き和紙の製造は、熟練の技術と長年の経験を必要とする非常に手間のかかる作業です。しかし、その技術を継承する若い世代が減少しており、深刻な後継者不足に直面しています。
その要因の一つとして、技術習得の機会が限られていることが挙げられます。多くの工房が家族経営であり、後継者を育てる余裕がない場合も少なくありません。また、後継者育成には時間と費用がかかり、多くの工房にとって大きな負担となっていることも、後継者不足に拍車をかけています。
機械漉き和紙の普及
大量生産が可能な機械漉き和紙の普及も、手漉き和紙の需要減少に拍車をかけています。私たちが普段手にしている「和紙」と呼ばれるもののほとんどが、実は機械漉きです。機械漉き和紙は、手漉き和紙に比べて安価で安定した品質を保つことができるため、商業用の印刷物や包装紙など、大量消費される分野でも広く利用されています。しかし近年、機械漉き和紙も原材料の高騰や価格競争などの影響を受け、廃業に追い込まれるケースが増加しています。
ライフスタイルの変化
現代のライフスタイルの変化も、手漉き和紙の需要減少に影響を与えています。洋風建築の増加やデジタル化の進展により、障子や襖、書道用紙など、伝統的な和紙の用途が減少しています。また、和紙の定義が広がり、多様な「和紙風」商品が出回るようになったことも、手漉き和紙の需要を低下させていると考えられます。生まれてから一度も本物の和紙に触れたことがない方も珍しくなく、こだわりをもって漉かれた手漉き和紙が埋もれてしまっているのが現状です。
コストの高騰
和紙原料の価格高騰や光熱費の上昇は、手漉き和紙の価格上昇に直結しています。その結果、本物の手漉き和紙は手軽に購入できるものではなくなり、需要の減少に拍車をかけています。
また、原料を海外産原料や洋紙原料の木材パルプなど安価なものに切り替えても、大量生産によるコスト優位性を持つ機械漉き和紙との価格競争にさらされます。結果として、手漉き和紙職人は「本物を作っても売れない、安い物を作れば売れるけど、本来の和紙からかけ離れたものになる」というジレンマに直面しています。
手漉き和紙の未来を守るために
今回は、手漉き和紙が少なくなってしまっている背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていることをご紹介しました。しかし、こうした困難な状況を乗り越え、伝統を守り続ける和紙職人たちが今もなお日本各地で活躍しています。彼らの漉く一枚一枚の和紙には、長い歴史と熟練の技、そして和紙への深い愛情が込められています。
弊社は和紙専門店として、職人たちが丹精込めて漉き上げた和紙の魅力をより多くのお客様にお伝えし、日本の伝統工芸を守り、未来へと繋いでいきたいと考え様々な取り組みを行っています。手漉き和紙の温もりや風合い、そしてその歴史に触れていただき、和紙のある暮らしを楽しんでいただければ幸いです。
※参考記事
日本全国にある和紙の産地一覧と、それぞれの地域の代表的な和紙についてご紹介。
年々厳しさを増す日本の和紙業界。私たちにできることを、今一度共に考えます。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:日本で有名な和紙は何ですか?
2018年08月26日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

日本の伝統文化のひとつである和紙。その歴史は古く、平安時代にはすでに高品質な和紙が作られていました。原料となる植物や製法によって多様な種類があり、それぞれが持つ独特の風合いが魅力です。今回は、日本を代表する和紙についてご紹介します。
日本三大和紙
日本には数多くの種類の和紙がありますが、その中でも特に「日本三大和紙」と呼ばれるものがあります。それぞれ特徴が異なり、長い歴史と伝統を持っています。
- 越前和紙(福井県)
日本初の紙幣に使用されたことでも知られる越前和紙は、その丈夫さと美しさが特徴です。国宝・文化財の保存や復元にも用いられるなど、その高い品質が評価されています。近年では、消臭・抗菌効果も認められ、宇宙産業をはじめとする様々な分野で活躍の場を広げています。1976年には国の伝統的工芸品に指定されました。
- 美濃和紙(岐阜県)
薄くても丈夫で、ムラのない均一な美しさが特徴です。障子紙や表具用紙など、伝統的な用途から生活雑貨まで幅広く用いられています。1969年に国の重要無形文化財、1985年に伝統的工芸品に指定され、2014年には「本美濃紙」の手漉き技術がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、その価値が世界的に認められています。
- 土佐和紙(高知県)
多種多様な種類があり、薄さと丈夫さを兼ね備えた和紙として知られています。中でも、文化財の修復に主に使用される「土佐典具帖紙」は、別名「かげろうの羽」とも呼ばれ、和紙としては極めて薄い0.03〜0.05mmの厚さが特徴です。1976年には国の伝統的工芸品に指定されました。
その他の有名な和紙
日本三大和紙以外にも、多くの地域で伝統的な和紙が作られています。下記はその一例です。本記事をご覧いただいている方の地元にも、紙漉きの里があるかもしれません。この機会にぜひ調べてみてください。
- 細川紙(埼玉県)
繊維が均一に絡み合い、紙面にけばだちが生じにくく、きわめて強靱なことが特徴です。その優れた品質から、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。
- 石州半紙(島根県)
古くは障子紙や書道用紙として、人々の生活を支えてきました。弾力のある強靭性と、驚くほどの軽さや柔らかさという対照的な特徴を持ち合わせています。ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
- 二俣和紙(石川県)
優れた耐久性と柔らかな質感を持つ二俣和紙は、加賀藩が幕府に提出する公文書に採用され「加賀奉書」の名で呼ばれるなど、古くから上質な和紙として知られています。現在では、斎藤博氏により伝統が受け継がれ、楮の栽培から紙漉きまでを一貫して行うことで、伝統の製法を忠実に守り続けています。

和紙の魅力とは?
和紙の魅力は、自然素材が持つ温かみのある風合いと、その多様性にあります。楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)などの植物の繊維を原料とし、職人の手によって漉き上げられることで、独特の温もりと奥深い味わいが生まれます。書道や絵画、工芸品、さらには現代的なインテリアまで、その用途は多岐にわたり、私たちの生活に豊かな彩りを添えてくれます。
最後に
一枚一枚に込められた職人の手仕事、そして長い歴史の中で培われた技術。和紙に触れることは、単に美しい紙を見るだけでなく、日本の文化や自然、そして人々の営みを感じさせてくれます。
直接、和紙の産地に訪れてみることもおすすめです。和紙の産地では、その土地で漉かれた和紙が販売されていたり、職人が実際に紙を漉く様子を見学することもできます。五感を使ってその土地の空気感や、和紙が生まれる工程を体験することで、和紙の素晴らしさを改めて実感できます。和紙作りに適した環境は、基本的に自然豊かな場所なので、良い気分転換にもなります。
現代社会はデジタル化が進み、便利になった一方で、人々は手作りの温もりや自然素材の風合いを求めるようになりました。それは、デジタル化がもたらす便利さだけでは満たされない「心の豊かさへの渇望」なのかもしれません。和紙は、そんな私たちに心の安らぎと潤いを与え、暮らしをより豊かに彩る、かけがえのない存在なのです。
※参考記事
和紙漉き体験でも、価格に大きな差があることをご存知でしょうか。その価格差が生まれる理由を解説しています。
日本最古の和紙の一つである美濃和紙にスポットをあてて、その歴史や特徴を解説しています。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:日本最古の和紙は、いつどこで作られたものですか?
2018年07月24日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****
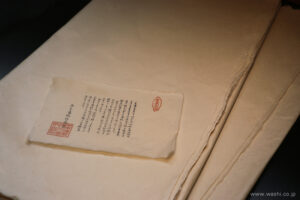
「和紙」と聞くと、日本の伝統文化を象徴するような、古くからある素材というイメージが浮かびます。では、日本最古の和紙は一体いつ、どこで作られたものなのでしょうか?今回は、日本最古の和紙の一つである美濃和紙にスポットをあてて、その歴史や特徴をご紹介します。
現存する日本最古の和紙
現存する日本最古の和紙は、奈良の正倉院に収蔵されている702年(大宝2年)の戸籍用紙です。この戸籍用紙は、美濃(みの/岐阜県南部)、筑前(ちくぜん/福岡県西北部)、豊前(ぶぜん/福岡県東半部と大分県北部)の3国で作られており、特に美濃で作られた和紙は、漉きムラが少なく紙質が一番優れていたとされています。
美濃和紙の歴史
美濃和紙は、戸籍用紙の存在からもわかるように、非常に長い歴史を持つ日本の伝統工芸品です。良質な原料と清流に恵まれた岐阜県美濃地方では、1300年以上前から和紙作りが行われてきました。
近代以降は、ウィーンやパリ万博などでの紹介を通じて、その名が世界に広まりました。特に、原料や製法が厳格に定められた「本美濃紙」の製作技術は、1969年に国の重要無形文化財、1985年には国の伝統的工芸品、そして2014年にはユネスコ無形文化遺産に登録され、その高い技術が評価されています。
- 奈良時代
経典の写経や家系図などの政府の記録に用いられました。
- 平安時代以降
紙の需要が高まり、美濃和紙は高品質な紙として広く利用されるようになりました。
- 江戸時代
高級障子紙として最上の評価を受け「美濃判」という規格も生まれました。
美濃和紙の特徴
美濃和紙は、薄くても丈夫で、ムラのない均一な美しさが特徴です。その秘密は、良質な原料と清流、そして独特の漉き方にあります。美濃の手漉き職人は、紙を漉く際に、縦だけでなく横方向にも揺らし、繊維をより密に絡ませます。古くから障子紙として用いられることの多かった美濃和紙は、光を透かすとその美しさが際立ちます。現在では、伝統的な製法を守りながら、現代の生活に合う様々な製品が作られています。
美濃和紙と本美濃紙の違い
「美濃和紙」は、岐阜県美濃地方で作られる和紙の総称です。機械漉きのものも含め、広範囲に用いられます。一方「本美濃紙」は、重要無形文化財に指定された材料や道具を用い、選ばれた職人だけが漉くことを許された、美濃和紙の最高峰の手漉き和紙です。
かつて「美濃和紙」と言えば、伝統的な手漉き和紙を指していました。しかし、木材パルプを混ぜた和紙が増えたことで、区別する必要性が生まれ「本美濃紙」という名称を定めて、呼ばれるようになりました。
美濃和紙から学ぶ
美濃和紙は「本美濃紙」という厳格な基準を設けることで、伝統的な製法を守り続けてきました。しかし日本全体で見ると、和紙が広い範囲で定義されるようになり、各産地の本物の手漉き和紙の価値が十分に評価されていないのが現状です。一度広まった定義を変えることは容易ではありませんが、各産地が美濃和紙のように厳格な基準を設けることで、より多くの消費者に本物の手漉き和紙の魅力を知ってもらうことができるのではないでしょうか。弊社も微力ながら、今後も正しい情報をお客様にお伝えし、本物の和紙文化の継承に貢献していきます。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:和紙の歴史について教えてください。
2018年06月24日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

古来より日本人の暮らしに深く根ざしてきた和紙。その歴史は、実に1400年以上にも及びます。書道や絵画、工芸品など、様々な分野で用いられてきた和紙は、単なる紙というだけでなく、日本の文化や美意識を象徴する存在といえます。今回は、そんな和紙の歴史を簡単に分かりやすく紐解いていきます。
和紙の歴史
紙の伝来と日本の独自性
- 紙の伝来
日本最古の歴史書のひとつ「日本書記」によると、610年に高句麗(こうくり)の僧である曇徴(どんちょう)によって、紙の製造技術が日本に持ち込まれたと記されています。高句麗は現在の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国北部から満洲の南部にかけての地域に存在した国家です。
- 日本の独自性
日本では、持ち込まれた技術を基に、独自の素材や製法を開発し、和紙へと発展させました。特に、楮(こうぞ)や三椏、雁皮といった植物の繊維を原料とし、「流し漉き」という独特の製法が確立されました。この製法により、強靭で美しい和紙が作られるようになったのです。現在における和紙の定義については、こちらの記事をご覧ください。
各時代の和紙
- 平安時代
貴族の間で書道や和歌が盛んになり、和紙は書物や手紙などに広く利用されました。また、障子や襖などの建具にも使用され、日本独自の美意識を表現する上で重要な役割を果たしました。
- 鎌倉時代~江戸時代
武家社会の成立とともに、和紙は武具や書状などにも利用されるようになりました。江戸時代にはいると庶民の間にも広まり生産量が急増。浮世絵の台頭により、版画用の紙としても需要が高まりました。
- 明治時代以降
洋紙の普及により、和紙の需要は減少しましたが、その美しさや機能性から、工芸品や美術品としての価値が見直され、新たな展開を見せています。2014年にはユネスコが「和紙 日本の手漉和紙技術」を無形文化遺産に登録。登録されたのは本美濃紙(岐阜県)、細川紙(埼玉県)、石州半紙(島根県)で、これらに共通するのは国産の楮のみを原料としている点です。
和紙は、長い歴史の中で培われた日本の伝統と技術の結晶です。現代においては、生活必需品ではなくなりましたが、その美しさ、機能性、そして表現力は、私たちの生活を豊かにする存在です。まるで空気のように「なくてはならないもの」とまではいかないまでも、和紙が世の中からなくなると、私たちの暮らしから何か大切なものが失われてしまうように感じます。弊社では、そんな可能性を秘めた和紙をもっと身近な存在にし、多くの方に魅力を伝えていくことで、和紙文化の継承に貢献したいと考えています。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
和紙のQ&A:和紙はどんな用途に使われていますか?
2018年05月23日
*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

和紙の魅力と多様な用途
和紙は、その美しい風合いと優れた耐久性から、古くから日本人の生活に深く根付いています。原料となる植物繊維の種類や製法によって、様々な特徴を持つ和紙が生まれ、用途も多岐にわたります。今回は、幅広く活用されている和紙の用途をいくつかご紹介します。
和紙の主な用途
- 書画
書道、書画、日本画、写経、書物、色紙など
- 局紙
紙幣、証券など
- 工芸・日用品
葉書、便箋、和傘、懐紙、紙衣、扇子、うちわ、ぼんぼり、提灯、行灯、張り子、一貫張り、紙鍋、マスキングテープなど
- 建築資材
障子、襖、衝立、屏風、壁紙など
和紙の魅力とは?
- 自然素材の温もり
楮・三椏・雁皮などの自然素材から作られる和紙は、温かみのある風合いが特徴です。人工的な素材にはない、独特の肌触りと視覚的な美しさを楽しむことができます。
- 高い耐久性
良質な原料と伝統的な製法で作られた和紙は、長い繊維が複雑に絡み合うことで、非常に強靭な構造を持っています。古文書など、和紙だからこそ現代まで残っている貴重な資料も数多く存在します。
- 多様な表現力
和紙は、その原料や製法によって、無数の表情を見せます。薄くて透けるものから、厚くて丈夫なものまで、様々な種類があり、表現の幅も広いのが特徴です。
和紙は、その美しさ、耐久性、そして表現力といった多様な魅力を持つ素材です。伝統的な用途にとどまらず、現代においても様々な分野で活躍しています。こちらの記事では、和紙を使ったDIYをご紹介しています。この機会に、暮らしの中に和紙を取り入れてみてはいかがでしょうか。
和紙のよくある質問 一覧へ戻る
著者/この記事を書いた人
浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)
浅倉敏之
石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。